Vol.178 1日違いで大違い
平成26年中にゴルフ会員権を譲渡されたかた。
損失が出ている場合には、確定申告で注意が必要ですね。

譲渡が平成26年3月31日までか4月1日以後かで、大きく取り扱いが異なります。
自戒を込めて、週間税務通信の記事で確認しておこう。
△
ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合、
その損失を給与所得等の他の各種所得と相殺(損益通算)することで、
課税の対象となる全体の所得金額を少なくすることができたが、
26年4月1日以後譲渡したゴルフ会員権により生じた譲渡損失は、
他の各種所得区分と損益通算ができなくなった。
(略)
金地金等総合課税の譲渡所得として扱われるものに譲渡益がある場合、
その譲渡益とゴルフ会員権の譲渡損失の相殺(内部通算)をすることは、
平成26年4月1日以後に譲渡したゴルフ会員権であっても可能である。
▽
3月31日以前の譲渡なら、譲渡損を給与所得等と相殺可能。
結果、給与から天引きされていた所得税の還付も見込めますね。
4月1日以後の譲渡なら、これが不可能。
ただ、金地金、30万円超の貴金属や骨董品、競走馬。
こういった資産を譲渡して生じた譲渡益とは相殺が可能です。
駆け込みでゴルフ会員権を譲渡されたかたは、再度譲渡の日を確認しておく必要がありますね。
Vol.177 税制も国際化
税制って、毎年どんどん複雑化の道を辿っていますね。
「税負担を免れようとする行為を防ぐ必要がある。」
これが年々複雑化していく要因の一つですね。
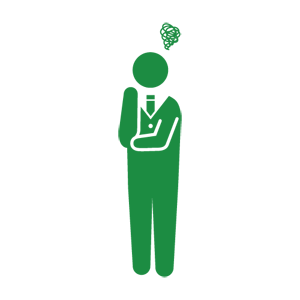
日経デジタルの記事です。
△
大手ゲームメーカー「タイトー」(東京都新宿区)のイスラエル人創業者(故人)の妻(当時89)が2013年に亡くなり、
国外で暮らしていた長男と長女が、海外にあった母親の財産約200億円にかかる相続税約110億円を滞納していることが分かった。
13年度の税制改正により、海外に住む相続人が相続した海外の財産についても日本国内で申告し、納税するよう制度が変わったが、
2人は「法律の周知期間が短すぎる」などと主張。国内財産分は納税したものの、海外財産分は滞納しているという。
▽
平成25年4月1日以後の相続や贈与については、
被相続人や贈与者が、相続時や贈与時に日本に住んでいれば、
相続人や受贈者が外国人でも、取得した「全財産」が相続税や贈与税の課税対象です。
で、この改正がされたのも、その背景があったわけで。
———————————————
父:「まさか、花子の結婚相手がマイケルとはなぁ。アメリカに行って、もう5年も経つんだなぁ(・・・シミジミ)」
母:「ほんとうにねぇ。孫の名前がキャサリンだなんて(苦笑)」
父:「そういえば、わしが死んでも、海外にある財産なら、花子が相続すれば相続税かからんのだよなぁ?」
母:「そうですねぇ。あの子はもう日本国籍もありませんものねぇ。」
父:「だったら、早いとこアメリカに財産を移しとこうか」
——————————————–
こんな話なら、まだ理解できますが。
なかには、わざわざ日本国籍から外国籍に変える。なんてケースも(^^;

相続人が外国籍になって、財産を海外へ移して相続税や贈与税を免れることへ対応したわけです。
どんどんと国際化が進んでいる近年、
昭和の時代には考えなかったことが起こるようになった。
時代に合わせて、人々の考えや行動も変化し、税制も変化を遂げていくわけですね。
Vol.176 すまい給付金の延長
所得税の確定申告シーズン真っ只中です。
合わせて、消費税の申告が必要な人の中には、
納税額の増え方に、驚愕されているんじゃないかなと。
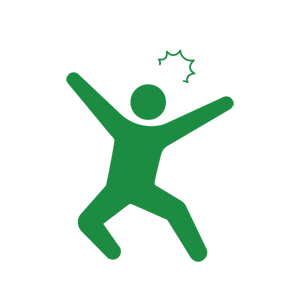
平成26年4月以降は、税率5%→税率8%ですから、6割増し。
去年に比べて売上が6割増しになることと比較すれば、
この増え方は、やっぱりインパクト大ですね(^^;
で、消費税の増税に対応するために、
「すまい給付金」が1年半延長になるそうな。
これから家を建てるかたには、ちょっとした朗報ですね。
今日のタビスランドより。
△
住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して
住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するための給付措置(すまい給付金)が設けられているが、
2月17日に行われた閣議で、このすまい給付金の対象期間を平成31年6月まで1年半延長することが決定した。
これにより、住宅取得に係る給付額(被災者の住宅再建の場合は除く)の目安(専業主婦、16歳以上の子ども1人の場合)は、
平成29年3月31日までの引渡し(平成29年4月1日以降の引渡しで、平成28年9月30日までの契約に係る経過措置の対象となる住宅を含む。)では、
収入額が425万円以下の場合で30万円、
425万円超475万円以下の場合で20万円、
475万円超510万円以下で10万円となる。
▽
増税になった消費税3%相当額と考えれば。
10万円なら、約340万円。
20万円なら、約670万円。
30万円なら、1,000万円。
これらの金額を超えた分の3%分は自己負担ですが。
住宅ローン控除などとの合わせ技を考えれば、随分と優遇されていますね。
ただ、資材も値上がりしているようですし、帳消しになるんじゃ・・・なんて気もしますが(^^;
Vol.175 奇妙な結果
空前の超低金利時代ですが。
出口は見えてきたのでしょうか。
今日の日経デジタルの記事です。
△
大手銀行が3月から住宅ローン金利を引き上げる。
三菱東京UFJ銀行が主力の10年固定型の最優遇金利を過去最低だった2月より0.1%引き上げて年1.2%とするのに続き、
みずほ銀行も引き上げを決めた。同じ10年固定金利を0.05%引き上げ1.15%にする。
両行が住宅ローン金利を引き上げるのは、指標となる市場金利が2月に入ってやや上昇したためだ。
長期金利の指標となる10年物国債利回りは1月に過去最低の0.195%まで低下していたが、
今月に入って一時0.45%まで上昇するなど動きが激しかった。
▽
とはいえ、相変わらずの低金利であることには間違いないですね。
住宅ローンの変動金利などでは、1%を切るでしょうし。
で、確定申告で住宅ローン控除を受けるとすれば、
1%が「税額」から控除されるわけですが。
つまり、1%未満の金利で住宅ローンをしていれば、
住宅ローン控除で得られる税額軽減効果の方が大きいケースもあると。
「借入したほうが得」なんて違和感ですが、事実は小説より奇なり・・・ですかね(^^;
さて、この奇妙な現象は、いつまで続くのでしょうか。
Vol.174 120年ぶり
成立当初のことを生で知る人はいないですね。
何しろ、120年ぶりの抜本改革といことですから。
今日の朝日デジタルの記事です。
△
1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、
現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。
法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜本改正となる。
▽
時効については、飲食代などのツケは1年、診療報酬は3年など、
ばらばらだったものを「原則5年」に統一するんですね。

改正自体は、適宜すれば良いのかなと思いますが。
それにしても、5年に統一とは・・・。
明治、大正、昭和に比べ、
格段に変化が速くなっている平成の時代に。

また、来月の通常国会で法案成立したとして、施行は2018年中を目指すということ。
それほどまでに慎重にしないといけないのでしょうかねぇ。
さらに、成人と未成年の違いなどを定めた「総則」
不動産の所有などについて定めた「物権」
結婚や相続について定めた「親族・相続」
これらは、化石化したまま残るのですね(^^;
Vol.173 マイナンバーの運用開始日、ご存知ですか?
確定申告シーズン真っ盛り。
先日、とあるお客様へ、確定申告書をお届けにあがったときのこと。
私:「今年の10月にはマイナンバーが交付されますね。」
お客様:「え?もう決まったんですか?」
私:「はい、法案は去年成立して、今年の10月から番号が交付されて、来年1月から実際に運用されますよ。」
まだ知らない人は沢山いるんだろうなとは思っていましたが。
世間一般でも、まだ知らない人だらけのようです。
今日のNHKニュースです。
△
国民1人1人に番号を割りふる「共通番号制度」、
いわゆる「マイナンバー制度」の運用が来年から始まるのを前に、
内閣府が制度の認知度などを調査したところ、制度の内容を知らない人が70%を上回っています。

▽
ん~、まだ少し時間はありますが、こんな状態で運用を始めて、混乱しないのかなぁ(^^;
マイナンバーについては、まずはこちらをどうぞ!
Vol.172 舵を切る
なるほど。消費者心理は冷えたままなのですね。
そりゃ、個人消費が増えないわけです。
今日の日経電子版の記事から。
△
日本経済新聞社とテレビ東京が20~22日に実施した世論調査で、
景気回復の実感を聞くと「実感していない」が81%に上り「実感している」は13%にとどまった。
▽
内訳をみたときに、
内閣支持層ですら、
景気回復を「実感していない」が73%、
「実感している」は23%ということです。

将来の不安が解消されないばかりでなく、
現在の景気動向にも、好転の実感がわかない。
消費税の増税、円安急進による輸入価格の高騰。
さらに、原油価格下落で石油元売り大手は大打撃。
外的要因も大きいのかもしれませんが、安倍総理の判断も大きいですね。
さて、この世論調査の結果を受けて、政府はどのように舵を切るのでしょうか。
何度か書いていますが、このままじゃダメってことは見えてるように思うのですが。
いかに円安主導をソフトランディングさせることが出来るか。
個人的には、ここに注目しています。

おかしいと感じたときには軌道修正。
みなさんは人生の舵取りを上手くできていますか?
Vol.171 最高裁の判断
「ハズレ馬券は経費に当たる」最高裁でも下級審と同様の判断ですね。
これで、今後の税法実務は、より難しくなるのかも・・・。
20日のタビスランドの記事です。
△
ハズレ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた脱税事件の裁判で、
「ハズレ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなった。
最高裁は二審での結論を見直す際に必要となる弁論を開かず、来月10日に判決を言い渡すことを決定した。
(略)
通常、馬券の払戻金による収入は、偶発的な収入として「一時所得」と見なされる。
一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、
収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたらない。
▽
この事件では、馬券の払戻金による収入が「雑所得」に当たるとの判断。
所得税法35条では、雑所得を「総収入金額から必要経費を控除した金額」としています。
一時所得の必要経費は「収入に『直接』要した金額」ですが、雑所得の必要経費は、その範囲が広い。
つまり、一時所得なら、当たり馬券の購入費用だけが必要経費になるところ、雑所得ならハズレ馬券も必要経費になる。
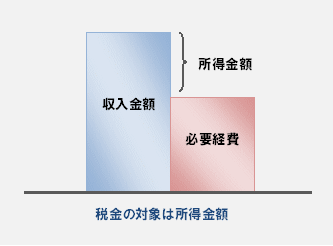
結果、多額の必要経費が認められて、所得税の負担は、圧倒的に減ったというわけ。
で、これがどのケースにも当てはまるはずはなく、あくまで、この事件についてはという判断ですね。
では、どこまでが一時所得で、どこからが雑所得になるのか。
ボーダーラインが見えないのは悩ましいですね。
この最高裁判決を信じて、雑所得で申告するには勇気がいるかも(^^;
Vol.170 難問です
「特定口座・源泉徴収あり」を選択している場合の、株の譲渡所得と配当所得の申告。
仕事柄、この時期に迷うことが多く、多分、税理士が共通して持つ悩みかなと。
申告すれば、所得税が還付になるケースでも、それだけでは選択不可能。

住民税がどうなるか、翌年の国民健康保険料がどうなるか。
さらには、高齢者のかたなら、医療費の自己負担割合が1割で収まるか。
はては、仮に翌年の国民健康保険料が申告しない場合に比べて増えるとしても、
国民健康保険料は、翌年の所得税・住民税の控除になるので、そこまで考えると・・・などなど。
要は、税金で払おうが、社会保険料で払おうが、医療費で払おうが、
懐から出ていくお金であることには変わりはないってことですね。
その出ていくお金を、トータルでどれだけ減らせるかってこと。

ただ、翌年の所得がいくらになるかなんて、予想することは難しいですね。
翌年どれだけ病院等のお世話になるかなんて、誰にも分からない。
仮に予想できたとしても、その通りに行くかどうか・・・。
まさに雲をつかむような話ですよね。

さて、税理士はどこまで考えて申告するかの判断をするべきなのだろう・・・
Vol.169 時代とともに税制も変わる・・・
もし、贈与税がなかったら。
将来、多額の相続税が課されると予想されても、
財産を子供たちに贈与してしまえば、相続税の問題はクリア。
贈与税があるから、このような相続税逃れは、短期間ではできないわけです。

これが、「贈与税は相続税の補完税」と言われる所以なのですが。
何度か書いていますが、どうも、贈与税が「富裕層優遇」の制度に変化しつつあるような・・・。
今日のタビスランドでも、同様の指摘がされています。
△
個人資産の流動化を税制が後押しする動きが加速している。
今年1月から税率構造の見直し・基礎控除引下げによる相続税増税がスタートしているが、
その一方で、平成27年度税制改正には贈与税の緩和措置がふんだんに盛り込まれており、
個人資産を次世代に引き継ぎやすくする環境が急速に整いつつある。
(略)
相続税の補完税という位置づけであった贈与税だが、ここへきてその役割は大幅に変わりつつある。
▽
経済対策・景気対策の名のもとに、贈与税軽減に拍車がかかる。
富裕層を優遇することで、貧富の格差を助長する制度になってしまうのだろうか。
高齢者から財産を奪い取り、若年層の浪費を助長する制度になってしまうのだろうか。
本来の立ち位置を見失い、税理士をはじめ一部業界の営業ツールと化してしまうのだろうか。
その裏返しとして、贈与税軽減を営業ツールとして利用できない人たちは、淘汰されていくのだろうか。

 ホーム
ホーム
